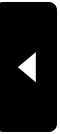「五月人形」の記事一覧
スポンサーリンク
夜、一人でトイレ行かれへん・・・。
最近、世の中が優しくなっています。
僕が夢中になっていた仮面ライダー1号、2号の頃(年代バレバレ)は
単純明快でした。
正義は正義、悪者は悪者。
ライダーが「ええもん」でショッカーは「悪魔の軍団」で「わるもん」。
水戸黄門に代表されるような「勧善懲悪」でなく、
「悪いことをした側にもそれなりの事情があったはずだ」という声も。
ともすれば、被害者より加害者の方が社会的に保護されているのではないか、
と疑念を抱かざるをえないこともままあります。
さて、五月人形、特に鎧をご覧になられたお客様からは
「勇ましい」
「かっこいい」
「美しい」
と我々にとっては嬉しい評価だけでなく、
「こわい」
「こんなんウチにあったらオレ夜トイレに一人で行かれへんわ」
という声もお聞きします。

何か睨みつけてるし・・・・。
そうです。鎧は見た目は怖いものなのです。
実際の武具であった甲冑は、戦場ではハッタリでもよいから自分を強く見せる必要があったことでしょう。
ましてや、存在意義が魔除け、厄除けである彼らお節句の鎧、兜たちにとっては、
お子さんたちに振りかかろうとする災いや厄を睨みつけ退散させる、
そんなパワーがなくてはなりません。
それでも、
子供が見たら泣きだしそう、そう思われる親御さんもいらっしゃるでしょう。
ウチの四歳の息子は張子の虎を見せると逃げ出します。
最初の頃はそうかもしれませんね。
でも、鎧を見ても泣かないようになったらシメたものです。
ひょっとしたら、五月人形との対面は、
お子さんにとって、初めて勇気を出さなければいけない時、なのかも。
男の子の節句物なんてものは、怖くなければ意味がない、僕はそう思っています。
古いTVドラマの話ばかりで恐縮ですが、
「独眼竜政宗」で、幼少の伊達政宗(藤間良太 日本舞踊家 現 藤間勘十郎)が
大滝秀治演ずる虎哉禅師から不動明王が何たるかを説かれ、
「梵天丸もかくありたい」
とつぶやいたシーンを思い出しました。
僕が夢中になっていた仮面ライダー1号、2号の頃(年代バレバレ)は
単純明快でした。
正義は正義、悪者は悪者。
ライダーが「ええもん」でショッカーは「悪魔の軍団」で「わるもん」。
水戸黄門に代表されるような「勧善懲悪」でなく、
「悪いことをした側にもそれなりの事情があったはずだ」という声も。
ともすれば、被害者より加害者の方が社会的に保護されているのではないか、
と疑念を抱かざるをえないこともままあります。
さて、五月人形、特に鎧をご覧になられたお客様からは
「勇ましい」
「かっこいい」
「美しい」
と我々にとっては嬉しい評価だけでなく、
「こわい」
「こんなんウチにあったらオレ夜トイレに一人で行かれへんわ」
という声もお聞きします。

何か睨みつけてるし・・・・。
そうです。鎧は見た目は怖いものなのです。
実際の武具であった甲冑は、戦場ではハッタリでもよいから自分を強く見せる必要があったことでしょう。
ましてや、存在意義が魔除け、厄除けである彼らお節句の鎧、兜たちにとっては、
お子さんたちに振りかかろうとする災いや厄を睨みつけ退散させる、
そんなパワーがなくてはなりません。
それでも、
子供が見たら泣きだしそう、そう思われる親御さんもいらっしゃるでしょう。
ウチの四歳の息子は張子の虎を見せると逃げ出します。
最初の頃はそうかもしれませんね。
でも、鎧を見ても泣かないようになったらシメたものです。
ひょっとしたら、五月人形との対面は、
お子さんにとって、初めて勇気を出さなければいけない時、なのかも。
男の子の節句物なんてものは、怖くなければ意味がない、僕はそう思っています。
古いTVドラマの話ばかりで恐縮ですが、
「独眼竜政宗」で、幼少の伊達政宗(藤間良太 日本舞踊家 現 藤間勘十郎)が
大滝秀治演ずる虎哉禅師から不動明王が何たるかを説かれ、
「梵天丸もかくありたい」
とつぶやいたシーンを思い出しました。
青葉の笛
これから書くことは人形選びとはあまり関係がありません。
この時期になると「平家物語」を読み返したくなります。
店内で流している唱歌や童謡にまじり、
「青葉の笛」を耳にすることも多くなりました。
滅びゆく平家の公達を題材にした歌で
一番は 敦盛。
熊谷直実に討たれる年若の敦盛。
直実にしてみれば我が子と同い年くらいの敵を討たねばならない躊躇。
その慙愧。
須磨の平家の陣から聞こえてきていた笛の音の主はこの少年だったのか。
二番は 忠度(ただのり)。
都落ちに際し、歌の師に自らの詠んだ歌集を託す。
討たれる間際まで身に付けていた箙(えびら 矢の入れ物)に結わえた一葉の短冊。
行き暮れて 木の下陰を宿とせば 花や今宵の 主ならまし
お祝いとは全く逆のかなりネガティブな話になってしまいました。
小林秀雄は、平家物語は快活さ、明るさがある、みたいなことを書いていたけど、
やっぱり根底にあるのは無常観かな。
散りゆく桜を潔しと愛でる日本人の美学、美意識に通じるものではあるけど。
節句人形を扱っているからこそか、
こんなことをふと思い出してしまいます。

この時期になると「平家物語」を読み返したくなります。
店内で流している唱歌や童謡にまじり、
「青葉の笛」を耳にすることも多くなりました。
滅びゆく平家の公達を題材にした歌で
一番は 敦盛。
熊谷直実に討たれる年若の敦盛。
直実にしてみれば我が子と同い年くらいの敵を討たねばならない躊躇。
その慙愧。
須磨の平家の陣から聞こえてきていた笛の音の主はこの少年だったのか。
二番は 忠度(ただのり)。
都落ちに際し、歌の師に自らの詠んだ歌集を託す。
討たれる間際まで身に付けていた箙(えびら 矢の入れ物)に結わえた一葉の短冊。
行き暮れて 木の下陰を宿とせば 花や今宵の 主ならまし
お祝いとは全く逆のかなりネガティブな話になってしまいました。
小林秀雄は、平家物語は快活さ、明るさがある、みたいなことを書いていたけど、
やっぱり根底にあるのは無常観かな。
散りゆく桜を潔しと愛でる日本人の美学、美意識に通じるものではあるけど。
節句人形を扱っているからこそか、
こんなことをふと思い出してしまいます。

龍と虎!
「青春」という言葉はよく知られています。
春が青いならば、夏は?、秋は?、冬は?
人の一生と季節をリンクさせて捉えたのでしょうか。
それぞれ
人生真っ盛り、熱いぜ、燃えるような「朱夏」、
少し落ち着いたのか、いや実りの多い涼しげな「白秋」、
生の終焉をひかえ、達観したかのような「玄冬」。
身近では一日の移ろいもよく似ています。
朝、東から陽が昇る。
昼、太陽が一番高いところに南中する。
夕、やがて西の空に陽は沈み、
夜、深い闇に包まれる。
一日の動き、季節の巡り、人の一生と方角を関連付け、
「四神」が想像されました。
東に青龍、南に朱雀、西に白虎、北に玄武。
整理すると
春 → 夏 → 秋 → 冬
東 → 南 → 西 → 北
龍 → 雀 → 虎 → (玄)武
青 → 朱 → 白 → 玄(黒)
大阪の東、東大阪には「ホテルセイリュウ」があり、
会津には「白虎隊」がいましたし、
「北原白秋」という詩人もいました。
大相撲春場所ももうすぐですが、土俵の天蓋の四隅には
この四色の房が下げられています。
案外なじみ深いものとわかります。
これも余談ですが、
日本語の色を表す形容詞は、実は元々この四色しかありません。
あおい、あかい、しろい、くろい。
他の色は全て〇〇色い、という使い方をします。
例えば、きいろい、ちゃいろい、など。
緑色は青の範疇です。青々とした若葉、などと。
青信号の色は何色をしていますか?
五月人形の屏風などにも龍と虎の構図がよく用いられています。
単に雄壮だからでなく、
ここにも魔除けの意味合いがあります。
東の龍と西の虎がにらみ合っている。
わかりやすく言えば、強いヤツ二人がガンの飛ばしあいをしている、
その間には誰も怖くて入っていけない、そんな状態。

龍虎のコンビの他方、玄武と朱雀。
玄武も想像上の存在で、亀の上に蛇が乗っています。
いつしか玄武は亀に、孔雀は鶴に置き換えられ、鶴亀として
こちらもおめでたいものとして捉えられています。
春が青いならば、夏は?、秋は?、冬は?
人の一生と季節をリンクさせて捉えたのでしょうか。
それぞれ
人生真っ盛り、熱いぜ、燃えるような「朱夏」、
少し落ち着いたのか、いや実りの多い涼しげな「白秋」、
生の終焉をひかえ、達観したかのような「玄冬」。
身近では一日の移ろいもよく似ています。
朝、東から陽が昇る。
昼、太陽が一番高いところに南中する。
夕、やがて西の空に陽は沈み、
夜、深い闇に包まれる。
一日の動き、季節の巡り、人の一生と方角を関連付け、
「四神」が想像されました。
東に青龍、南に朱雀、西に白虎、北に玄武。
整理すると
春 → 夏 → 秋 → 冬
東 → 南 → 西 → 北
龍 → 雀 → 虎 → (玄)武
青 → 朱 → 白 → 玄(黒)
大阪の東、東大阪には「ホテルセイリュウ」があり、
会津には「白虎隊」がいましたし、
「北原白秋」という詩人もいました。
大相撲春場所ももうすぐですが、土俵の天蓋の四隅には
この四色の房が下げられています。
案外なじみ深いものとわかります。
これも余談ですが、
日本語の色を表す形容詞は、実は元々この四色しかありません。
あおい、あかい、しろい、くろい。
他の色は全て〇〇色い、という使い方をします。
例えば、きいろい、ちゃいろい、など。
緑色は青の範疇です。青々とした若葉、などと。
青信号の色は何色をしていますか?
五月人形の屏風などにも龍と虎の構図がよく用いられています。
単に雄壮だからでなく、
ここにも魔除けの意味合いがあります。
東の龍と西の虎がにらみ合っている。
わかりやすく言えば、強いヤツ二人がガンの飛ばしあいをしている、
その間には誰も怖くて入っていけない、そんな状態。

龍虎のコンビの他方、玄武と朱雀。
玄武も想像上の存在で、亀の上に蛇が乗っています。
いつしか玄武は亀に、孔雀は鶴に置き換えられ、鶴亀として
こちらもおめでたいものとして捉えられています。
龍!
二枚の画像の兜を見比べてください。
違いがお分かりでしょうか?


一方には龍の飾り(前立物)があり、鍬形も細く長い形をしています。
他方は龍がなく、太く短い鍬形が据えられています。
10年ほど前までは前者の長鍬形のものが圧倒的多数を占めていました。
大鍬形のものもありましたが、人気があったのは龍の付いた兜でした。
それが最近、龍がないほうが
「シンプルでよい」、
「龍が嫌い」
というお客様が目立つようになりました。
実際、現存する12,3世紀頃の甲冑を調べてみても龍の付いた兜は殆ど見受けられません。
それどころか鍬形(実は鍬形も前立物の一種なのですが)すらないものも結構あります。
時代がもっと後になって戦国時代の頃の兜の前立はもっと個性豊かです。
蒲生氏郷の兜にはなまずが付いていましたし、
以前挙げた直江の「愛」の字、伊達政宗の「弦月」は有名です。
そうそう政宗の従兄弟成実(しげざね)は毛虫でした。
毛虫は後ろに動かない(実際は動けない)、敵に相対しても退かない勇気をあらわすもの、らしいです。
またまた余談ですが大河ドラマ「独眼竜政宗(主演は渡辺謙)」で成実を演じていたのは三浦友和でした。
龍のついた兜は源氏八領のうちの一つ「八龍」が、文献から推察するに
そうだったのではないかな、というぐらいです。
ちなみに源氏の武者が所用したと伝えられる源氏八領
は一つを残し全て消失しています。
この話についてはまた後日。
それだけ稀有なものであるのに、
お節句の鎧兜には当たり前のように付いていました。
登龍門を登りきった鯉だけが「龍」に化身、出世できる、「登龍門伝説」は
中国由来のものですが、 龍は出世の象徴 なのでしょう。
願わくば、無事の育成、更には立身出世。
いつの時代も親御さんの思いは同じだと思います。
故に、男の子のお節句飾りのメインである兜には龍を戴き、
屋外には鯉のぼりを高々と掲げる、ようになったのではないかと解釈しています。
ちなみに(が多いですが)姿、かたちはよく似ていますが、
西洋ギリシャ神話に端を発するドラゴンと 東洋の龍は似て非なるもの、全然違います。
前者は化け物、モンスターですが、
龍は「龍神」、神様であり、中国では皇帝の印でもありました。
「わし中日嫌いやねん」はナシでよろしく。
違いがお分かりでしょうか?


一方には龍の飾り(前立物)があり、鍬形も細く長い形をしています。
他方は龍がなく、太く短い鍬形が据えられています。
10年ほど前までは前者の長鍬形のものが圧倒的多数を占めていました。
大鍬形のものもありましたが、人気があったのは龍の付いた兜でした。
それが最近、龍がないほうが
「シンプルでよい」、
「龍が嫌い」
というお客様が目立つようになりました。
実際、現存する12,3世紀頃の甲冑を調べてみても龍の付いた兜は殆ど見受けられません。
それどころか鍬形(実は鍬形も前立物の一種なのですが)すらないものも結構あります。
時代がもっと後になって戦国時代の頃の兜の前立はもっと個性豊かです。
蒲生氏郷の兜にはなまずが付いていましたし、
以前挙げた直江の「愛」の字、伊達政宗の「弦月」は有名です。
そうそう政宗の従兄弟成実(しげざね)は毛虫でした。
毛虫は後ろに動かない(実際は動けない)、敵に相対しても退かない勇気をあらわすもの、らしいです。
またまた余談ですが大河ドラマ「独眼竜政宗(主演は渡辺謙)」で成実を演じていたのは三浦友和でした。
龍のついた兜は源氏八領のうちの一つ「八龍」が、文献から推察するに
そうだったのではないかな、というぐらいです。
ちなみに源氏の武者が所用したと伝えられる源氏八領
は一つを残し全て消失しています。
この話についてはまた後日。
それだけ稀有なものであるのに、
お節句の鎧兜には当たり前のように付いていました。
登龍門を登りきった鯉だけが「龍」に化身、出世できる、「登龍門伝説」は
中国由来のものですが、 龍は出世の象徴 なのでしょう。
願わくば、無事の育成、更には立身出世。
いつの時代も親御さんの思いは同じだと思います。
故に、男の子のお節句飾りのメインである兜には龍を戴き、
屋外には鯉のぼりを高々と掲げる、ようになったのではないかと解釈しています。
ちなみに(が多いですが)姿、かたちはよく似ていますが、
西洋ギリシャ神話に端を発するドラゴンと 東洋の龍は似て非なるもの、全然違います。
前者は化け物、モンスターですが、
龍は「龍神」、神様であり、中国では皇帝の印でもありました。
「わし中日嫌いやねん」はナシでよろしく。
どんなヨロイがいいのかなあ? その3
前回、鎧を構成する部分の名称はお洒落なものが多い、
と述べました。
今日もその続きです。
丁度胸から脇のあたりにかけて左右形の違う板がぶら下がっているのが
お分かり頂けるでしょうか。

左側(向かって右)には白い絵革(えがわ)を貼った盾のような板があります。
この板は弓を構えた時に脇を防御する板で、
鳩のしっぽのような形から「鳩尾(きゅうび)の板」といいます。
盾ですから形が変わらないよう一枚板で構成されています。
右側(向かって左)は、三段の黒い板を赤い紐で綴じ合わせているのが
お分かり頂けると思います。
右手は弓弦を引く手で、動きも大きい為、
脇を防御しつつも腕の動きを邪魔しないよう
「融通が利」かねばなりません。故に可動するように
板を紐でつなぐという工夫がなされました。
「三段の板」が転訛して「栴檀(せんだん)の板」といわれるようになりました。
ということになっています。
今述べたことはちょっとネットを調べればたどり着く話なのですが、
京都の鎧職人でもう亡くなられた先代の「一水」さん、今村勝男氏から
以下のような話を聞いたことがあります。
栴檀は双葉より香ばし、栴檀はよい芳香を放つ。
武者は出陣に際し、この三段の板の付け根部分に栴檀の香木を挿しはさんだ。
鎧を着て出て行くときは、即ち死ぬかもしれない覚悟を固めていく。
戦いに敗れ屍になった時、自らの腐臭を少しでも和らげるのが目的である。
総じて大鎧は当時の武者の美意識の象徴である、と。
この話を伺ったのはもう15年ほど前のことですが、
商品知識云々は別にして、衝撃的に感動しました。
ダンディズムはかくあるべし、と思いました。
大鎧は最高の装いであったのです。
と述べました。
今日もその続きです。
丁度胸から脇のあたりにかけて左右形の違う板がぶら下がっているのが
お分かり頂けるでしょうか。
左側(向かって右)には白い絵革(えがわ)を貼った盾のような板があります。
この板は弓を構えた時に脇を防御する板で、
鳩のしっぽのような形から「鳩尾(きゅうび)の板」といいます。
盾ですから形が変わらないよう一枚板で構成されています。
右側(向かって左)は、三段の黒い板を赤い紐で綴じ合わせているのが
お分かり頂けると思います。
右手は弓弦を引く手で、動きも大きい為、
脇を防御しつつも腕の動きを邪魔しないよう
「融通が利」かねばなりません。故に可動するように
板を紐でつなぐという工夫がなされました。
「三段の板」が転訛して「栴檀(せんだん)の板」といわれるようになりました。
ということになっています。
今述べたことはちょっとネットを調べればたどり着く話なのですが、
京都の鎧職人でもう亡くなられた先代の「一水」さん、今村勝男氏から
以下のような話を聞いたことがあります。
栴檀は双葉より香ばし、栴檀はよい芳香を放つ。
武者は出陣に際し、この三段の板の付け根部分に栴檀の香木を挿しはさんだ。
鎧を着て出て行くときは、即ち死ぬかもしれない覚悟を固めていく。
戦いに敗れ屍になった時、自らの腐臭を少しでも和らげるのが目的である。
総じて大鎧は当時の武者の美意識の象徴である、と。
この話を伺ったのはもう15年ほど前のことですが、
商品知識云々は別にして、衝撃的に感動しました。
ダンディズムはかくあるべし、と思いました。
大鎧は最高の装いであったのです。
どんなヨロイがいいのかなあ? その2
今日は土曜日。
3月に入って初めての週末。
お店には五月人形や鯉のぼりを見にお客様がいらっしゃいました。
まだ皆さん下見というか、様子を眺めてられる方が多いようです。
折角のお祝いのお品ですから、偶数月の4月に入るまでに、
出来れば3月中に納めるのがよいでしょう。
日本人は割り切れる偶数よりも奇数を吉としてきました。
お節句も 正月、上巳(3月)、端午(五月)、七夕(7月)、重陽(ちょうよう 9月)
と奇数月に存在します。
前回取り上げた「大鎧(おおよろい)」。伊達に「大」の字を付けているのではありません。
この「大」は、大きいという意味よりもむしろ「正式な」という
意味合いのほうが強いと思われます。
時代的には丁度大河ドラマ「平清盛」の頃、
平安時代から鎌倉時代後期、南北朝時代の頃。
戦いが集団対集団になる前段階、
「一騎打ち」で雌雄を決していた頃。
飛び道具の「鉄砲」が存在せず、「弓矢」が主な武器であった時代。
太刀は切りあう為のものでなく、「首を掻く」のが主用途でした。
別のいいかたをすれば敵の放つ矢から身を守るに都合よく、
自らが馬上から矢を射るのに都合よく作られたものでした。
両方の肩の部分を防御する板のようなものは「大袖(おおそで)」といい、
盾のようなものです。
ちなみに鎧の各部分の名称はお洒落なものが多く、
例えば、単純に右や左とは言いません。
画像で示したのは左肩を防御するものですが、
左手は弓を持つほうの手であることから「弓手の袖(ゆんでのそで)」といいます。
対して右手は馬の手綱を持つからでしょうか「馬手(めて)の袖」といいます。

一方腰から下、太ももにかけてを防御する部分を「草摺(くさずり)」と呼びます。
この頃のものは主に前後左右4間(けん、と数えます)から構成されていました。
現代では考えられないほど草ぼうぼうだったのでしょうか。
草摺については左側を矢を射る方向に向ける側であるため、「射向(いむけ)の草摺」
といいます。
前は「正面の草摺」、
後ろは座るときに敷くようになるからでしょう、「居敷(いしき)の草摺」といいます。
話が少し脱線しました。
ではまた後日。
3月に入って初めての週末。
お店には五月人形や鯉のぼりを見にお客様がいらっしゃいました。
まだ皆さん下見というか、様子を眺めてられる方が多いようです。
折角のお祝いのお品ですから、偶数月の4月に入るまでに、
出来れば3月中に納めるのがよいでしょう。
日本人は割り切れる偶数よりも奇数を吉としてきました。
お節句も 正月、上巳(3月)、端午(五月)、七夕(7月)、重陽(ちょうよう 9月)
と奇数月に存在します。
前回取り上げた「大鎧(おおよろい)」。伊達に「大」の字を付けているのではありません。
この「大」は、大きいという意味よりもむしろ「正式な」という
意味合いのほうが強いと思われます。
時代的には丁度大河ドラマ「平清盛」の頃、
平安時代から鎌倉時代後期、南北朝時代の頃。
戦いが集団対集団になる前段階、
「一騎打ち」で雌雄を決していた頃。
飛び道具の「鉄砲」が存在せず、「弓矢」が主な武器であった時代。
太刀は切りあう為のものでなく、「首を掻く」のが主用途でした。
別のいいかたをすれば敵の放つ矢から身を守るに都合よく、
自らが馬上から矢を射るのに都合よく作られたものでした。
両方の肩の部分を防御する板のようなものは「大袖(おおそで)」といい、
盾のようなものです。

ちなみに鎧の各部分の名称はお洒落なものが多く、
例えば、単純に右や左とは言いません。
画像で示したのは左肩を防御するものですが、
左手は弓を持つほうの手であることから「弓手の袖(ゆんでのそで)」といいます。
対して右手は馬の手綱を持つからでしょうか「馬手(めて)の袖」といいます。

一方腰から下、太ももにかけてを防御する部分を「草摺(くさずり)」と呼びます。
この頃のものは主に前後左右4間(けん、と数えます)から構成されていました。
現代では考えられないほど草ぼうぼうだったのでしょうか。
草摺については左側を矢を射る方向に向ける側であるため、「射向(いむけ)の草摺」
といいます。
前は「正面の草摺」、
後ろは座るときに敷くようになるからでしょう、「居敷(いしき)の草摺」といいます。
話が少し脱線しました。
ではまた後日。
どんなヨロイがいいのかなあ?
先ほど投稿した記事を読み返しますと、
「何や、まだ半分だけかい!」
とお叱りを受けそうな内容だったので再投稿です。
当社は松屋町筋に4店舗展開しておりまして、
本店はもう既に五月人形、鯉のぼり全開バリバリの状態です。
さて、五月人形どんなのにしよう、と思案をめぐらせている方もいらっしゃるのでは?
お客様から
「伊達のカブトある?」
「直江の愛のヤツ欲しいねん」
などとよく問いかけられます。
ウチも商売ですから、売れそうなものは揃えておきます。
ちなみに
伊達の兜とは、兜のおでこのところに細長い三日月形の飾りのついているもの、
伊達政宗所用とされているものをいいます。
直江については一昨年でしたか、NHK大河ドラマ「天地人」の
直江兼続の 「愛」の飾り物のついた兜をいいます。
専門用語では前に付いている飾り物だから「前立物(まえたてもの)」といいます。
以下は僕の私見です。お気を悪くされたらごめんなさい。
「欲しい!」とおっしゃる方に「やめとけ」とはいいませんが、
ほんとにそれでいいのかな、と疑問も持っています。
お節句で飾る兜は、飽くまで「そのお子さんの物」。
それが
誰々の兜、でいいのかな、
誰のものでもない、普遍的な物
の方がいいことないかな、とずっと思ってきました。
上に挙げた二人の武将に対し、悪意はありません。
あくまで例として。
戦国武将で成功したのは「徳川家康」ただ一人です。
大多数は志半ばで斃れたり、「〇〇の覇者」などと修辞されはしますが、
所詮No.2までの存在でしかなかったり。
お子さんの未来はまだ真っ白です。
僕自身が好きな甲冑があります。
奈良の春日大社に所蔵されており、国宝の指定も受けている
「竹虎雀金物の大鎧」なのですが、

強いて言えば「春日大社の神さんの物」。
春日大社は藤原氏の氏神さんですから、まあこれも好みは分かれるでしょうか。
京都の職人さんが作っている甲冑も誰々の兜というのはあまり聞かないですね。
作り手として節句のお飾り、という大前提を弁えているからではないでしょうか。
「何や、まだ半分だけかい!」
とお叱りを受けそうな内容だったので再投稿です。
当社は松屋町筋に4店舗展開しておりまして、
本店はもう既に五月人形、鯉のぼり全開バリバリの状態です。
さて、五月人形どんなのにしよう、と思案をめぐらせている方もいらっしゃるのでは?
お客様から
「伊達のカブトある?」
「直江の愛のヤツ欲しいねん」
などとよく問いかけられます。
ウチも商売ですから、売れそうなものは揃えておきます。
ちなみに
伊達の兜とは、兜のおでこのところに細長い三日月形の飾りのついているもの、
伊達政宗所用とされているものをいいます。
直江については一昨年でしたか、NHK大河ドラマ「天地人」の
直江兼続の 「愛」の飾り物のついた兜をいいます。
専門用語では前に付いている飾り物だから「前立物(まえたてもの)」といいます。
以下は僕の私見です。お気を悪くされたらごめんなさい。
「欲しい!」とおっしゃる方に「やめとけ」とはいいませんが、
ほんとにそれでいいのかな、と疑問も持っています。
お節句で飾る兜は、飽くまで「そのお子さんの物」。
それが
誰々の兜、でいいのかな、
誰のものでもない、普遍的な物
の方がいいことないかな、とずっと思ってきました。
上に挙げた二人の武将に対し、悪意はありません。
あくまで例として。
戦国武将で成功したのは「徳川家康」ただ一人です。
大多数は志半ばで斃れたり、「〇〇の覇者」などと修辞されはしますが、
所詮No.2までの存在でしかなかったり。
お子さんの未来はまだ真っ白です。
僕自身が好きな甲冑があります。
奈良の春日大社に所蔵されており、国宝の指定も受けている
「竹虎雀金物の大鎧」なのですが、
強いて言えば「春日大社の神さんの物」。
春日大社は藤原氏の氏神さんですから、まあこれも好みは分かれるでしょうか。
京都の職人さんが作っている甲冑も誰々の兜というのはあまり聞かないですね。
作り手として節句のお飾り、という大前提を弁えているからではないでしょうか。
五月人形が出揃いました。
今日は3月2日
おひなまつりの前の晩を「宵節句」といいます。
実は当社の会長(私、筆者の父親で創業者)は3月3日が
誕生日で、ささやかながら私たち兄弟とそれぞれの連れ合い、孫みんなが集まって、一日早く誕生日と宵節句のお祝いをするのがここ数年の行事になりました。
まだ未就学の甥や姪の歌うおひなさまの歌は聞いていてほのぼのします。
さて、週末を目前に控え、店内は半分はひな人形、
もう半分は五月人形に衣替えが整いました。来週末には全部が五月人形に入れ替わります。

皆様のご来店をお待ち申し上げております。
おひなまつりの前の晩を「宵節句」といいます。
実は当社の会長(私、筆者の父親で創業者)は3月3日が
誕生日で、ささやかながら私たち兄弟とそれぞれの連れ合い、孫みんなが集まって、一日早く誕生日と宵節句のお祝いをするのがここ数年の行事になりました。
まだ未就学の甥や姪の歌うおひなさまの歌は聞いていてほのぼのします。
さて、週末を目前に控え、店内は半分はひな人形、
もう半分は五月人形に衣替えが整いました。来週末には全部が五月人形に入れ替わります。

皆様のご来店をお待ち申し上げております。


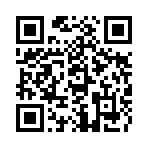
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン