「2012年03月04日」の記事一覧
スポンサーリンク
どんなヨロイがいいのかなあ? その3
前回、鎧を構成する部分の名称はお洒落なものが多い、
と述べました。
今日もその続きです。
丁度胸から脇のあたりにかけて左右形の違う板がぶら下がっているのが
お分かり頂けるでしょうか。

左側(向かって右)には白い絵革(えがわ)を貼った盾のような板があります。
この板は弓を構えた時に脇を防御する板で、
鳩のしっぽのような形から「鳩尾(きゅうび)の板」といいます。
盾ですから形が変わらないよう一枚板で構成されています。
右側(向かって左)は、三段の黒い板を赤い紐で綴じ合わせているのが
お分かり頂けると思います。
右手は弓弦を引く手で、動きも大きい為、
脇を防御しつつも腕の動きを邪魔しないよう
「融通が利」かねばなりません。故に可動するように
板を紐でつなぐという工夫がなされました。
「三段の板」が転訛して「栴檀(せんだん)の板」といわれるようになりました。
ということになっています。
今述べたことはちょっとネットを調べればたどり着く話なのですが、
京都の鎧職人でもう亡くなられた先代の「一水」さん、今村勝男氏から
以下のような話を聞いたことがあります。
栴檀は双葉より香ばし、栴檀はよい芳香を放つ。
武者は出陣に際し、この三段の板の付け根部分に栴檀の香木を挿しはさんだ。
鎧を着て出て行くときは、即ち死ぬかもしれない覚悟を固めていく。
戦いに敗れ屍になった時、自らの腐臭を少しでも和らげるのが目的である。
総じて大鎧は当時の武者の美意識の象徴である、と。
この話を伺ったのはもう15年ほど前のことですが、
商品知識云々は別にして、衝撃的に感動しました。
ダンディズムはかくあるべし、と思いました。
大鎧は最高の装いであったのです。
と述べました。
今日もその続きです。
丁度胸から脇のあたりにかけて左右形の違う板がぶら下がっているのが
お分かり頂けるでしょうか。
左側(向かって右)には白い絵革(えがわ)を貼った盾のような板があります。
この板は弓を構えた時に脇を防御する板で、
鳩のしっぽのような形から「鳩尾(きゅうび)の板」といいます。
盾ですから形が変わらないよう一枚板で構成されています。
右側(向かって左)は、三段の黒い板を赤い紐で綴じ合わせているのが
お分かり頂けると思います。
右手は弓弦を引く手で、動きも大きい為、
脇を防御しつつも腕の動きを邪魔しないよう
「融通が利」かねばなりません。故に可動するように
板を紐でつなぐという工夫がなされました。
「三段の板」が転訛して「栴檀(せんだん)の板」といわれるようになりました。
ということになっています。
今述べたことはちょっとネットを調べればたどり着く話なのですが、
京都の鎧職人でもう亡くなられた先代の「一水」さん、今村勝男氏から
以下のような話を聞いたことがあります。
栴檀は双葉より香ばし、栴檀はよい芳香を放つ。
武者は出陣に際し、この三段の板の付け根部分に栴檀の香木を挿しはさんだ。
鎧を着て出て行くときは、即ち死ぬかもしれない覚悟を固めていく。
戦いに敗れ屍になった時、自らの腐臭を少しでも和らげるのが目的である。
総じて大鎧は当時の武者の美意識の象徴である、と。
この話を伺ったのはもう15年ほど前のことですが、
商品知識云々は別にして、衝撃的に感動しました。
ダンディズムはかくあるべし、と思いました。
大鎧は最高の装いであったのです。


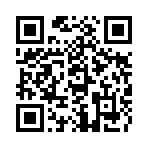
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン





