「2012年03月06日」の記事一覧
スポンサーリンク
青葉の笛
これから書くことは人形選びとはあまり関係がありません。
この時期になると「平家物語」を読み返したくなります。
店内で流している唱歌や童謡にまじり、
「青葉の笛」を耳にすることも多くなりました。
滅びゆく平家の公達を題材にした歌で
一番は 敦盛。
熊谷直実に討たれる年若の敦盛。
直実にしてみれば我が子と同い年くらいの敵を討たねばならない躊躇。
その慙愧。
須磨の平家の陣から聞こえてきていた笛の音の主はこの少年だったのか。
二番は 忠度(ただのり)。
都落ちに際し、歌の師に自らの詠んだ歌集を託す。
討たれる間際まで身に付けていた箙(えびら 矢の入れ物)に結わえた一葉の短冊。
行き暮れて 木の下陰を宿とせば 花や今宵の 主ならまし
お祝いとは全く逆のかなりネガティブな話になってしまいました。
小林秀雄は、平家物語は快活さ、明るさがある、みたいなことを書いていたけど、
やっぱり根底にあるのは無常観かな。
散りゆく桜を潔しと愛でる日本人の美学、美意識に通じるものではあるけど。
節句人形を扱っているからこそか、
こんなことをふと思い出してしまいます。

この時期になると「平家物語」を読み返したくなります。
店内で流している唱歌や童謡にまじり、
「青葉の笛」を耳にすることも多くなりました。
滅びゆく平家の公達を題材にした歌で
一番は 敦盛。
熊谷直実に討たれる年若の敦盛。
直実にしてみれば我が子と同い年くらいの敵を討たねばならない躊躇。
その慙愧。
須磨の平家の陣から聞こえてきていた笛の音の主はこの少年だったのか。
二番は 忠度(ただのり)。
都落ちに際し、歌の師に自らの詠んだ歌集を託す。
討たれる間際まで身に付けていた箙(えびら 矢の入れ物)に結わえた一葉の短冊。
行き暮れて 木の下陰を宿とせば 花や今宵の 主ならまし
お祝いとは全く逆のかなりネガティブな話になってしまいました。
小林秀雄は、平家物語は快活さ、明るさがある、みたいなことを書いていたけど、
やっぱり根底にあるのは無常観かな。
散りゆく桜を潔しと愛でる日本人の美学、美意識に通じるものではあるけど。
節句人形を扱っているからこそか、
こんなことをふと思い出してしまいます。

龍と虎!
「青春」という言葉はよく知られています。
春が青いならば、夏は?、秋は?、冬は?
人の一生と季節をリンクさせて捉えたのでしょうか。
それぞれ
人生真っ盛り、熱いぜ、燃えるような「朱夏」、
少し落ち着いたのか、いや実りの多い涼しげな「白秋」、
生の終焉をひかえ、達観したかのような「玄冬」。
身近では一日の移ろいもよく似ています。
朝、東から陽が昇る。
昼、太陽が一番高いところに南中する。
夕、やがて西の空に陽は沈み、
夜、深い闇に包まれる。
一日の動き、季節の巡り、人の一生と方角を関連付け、
「四神」が想像されました。
東に青龍、南に朱雀、西に白虎、北に玄武。
整理すると
春 → 夏 → 秋 → 冬
東 → 南 → 西 → 北
龍 → 雀 → 虎 → (玄)武
青 → 朱 → 白 → 玄(黒)
大阪の東、東大阪には「ホテルセイリュウ」があり、
会津には「白虎隊」がいましたし、
「北原白秋」という詩人もいました。
大相撲春場所ももうすぐですが、土俵の天蓋の四隅には
この四色の房が下げられています。
案外なじみ深いものとわかります。
これも余談ですが、
日本語の色を表す形容詞は、実は元々この四色しかありません。
あおい、あかい、しろい、くろい。
他の色は全て〇〇色い、という使い方をします。
例えば、きいろい、ちゃいろい、など。
緑色は青の範疇です。青々とした若葉、などと。
青信号の色は何色をしていますか?
五月人形の屏風などにも龍と虎の構図がよく用いられています。
単に雄壮だからでなく、
ここにも魔除けの意味合いがあります。
東の龍と西の虎がにらみ合っている。
わかりやすく言えば、強いヤツ二人がガンの飛ばしあいをしている、
その間には誰も怖くて入っていけない、そんな状態。

龍虎のコンビの他方、玄武と朱雀。
玄武も想像上の存在で、亀の上に蛇が乗っています。
いつしか玄武は亀に、孔雀は鶴に置き換えられ、鶴亀として
こちらもおめでたいものとして捉えられています。
春が青いならば、夏は?、秋は?、冬は?
人の一生と季節をリンクさせて捉えたのでしょうか。
それぞれ
人生真っ盛り、熱いぜ、燃えるような「朱夏」、
少し落ち着いたのか、いや実りの多い涼しげな「白秋」、
生の終焉をひかえ、達観したかのような「玄冬」。
身近では一日の移ろいもよく似ています。
朝、東から陽が昇る。
昼、太陽が一番高いところに南中する。
夕、やがて西の空に陽は沈み、
夜、深い闇に包まれる。
一日の動き、季節の巡り、人の一生と方角を関連付け、
「四神」が想像されました。
東に青龍、南に朱雀、西に白虎、北に玄武。
整理すると
春 → 夏 → 秋 → 冬
東 → 南 → 西 → 北
龍 → 雀 → 虎 → (玄)武
青 → 朱 → 白 → 玄(黒)
大阪の東、東大阪には「ホテルセイリュウ」があり、
会津には「白虎隊」がいましたし、
「北原白秋」という詩人もいました。
大相撲春場所ももうすぐですが、土俵の天蓋の四隅には
この四色の房が下げられています。
案外なじみ深いものとわかります。
これも余談ですが、
日本語の色を表す形容詞は、実は元々この四色しかありません。
あおい、あかい、しろい、くろい。
他の色は全て〇〇色い、という使い方をします。
例えば、きいろい、ちゃいろい、など。
緑色は青の範疇です。青々とした若葉、などと。
青信号の色は何色をしていますか?
五月人形の屏風などにも龍と虎の構図がよく用いられています。
単に雄壮だからでなく、
ここにも魔除けの意味合いがあります。
東の龍と西の虎がにらみ合っている。
わかりやすく言えば、強いヤツ二人がガンの飛ばしあいをしている、
その間には誰も怖くて入っていけない、そんな状態。

龍虎のコンビの他方、玄武と朱雀。
玄武も想像上の存在で、亀の上に蛇が乗っています。
いつしか玄武は亀に、孔雀は鶴に置き換えられ、鶴亀として
こちらもおめでたいものとして捉えられています。


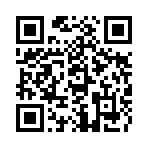
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン





